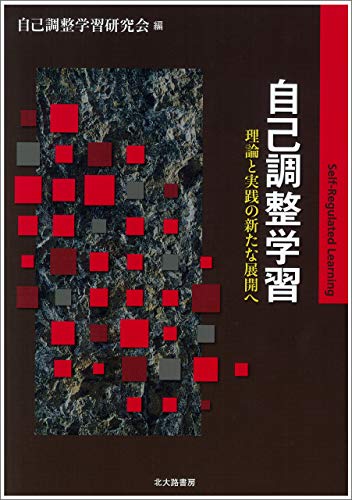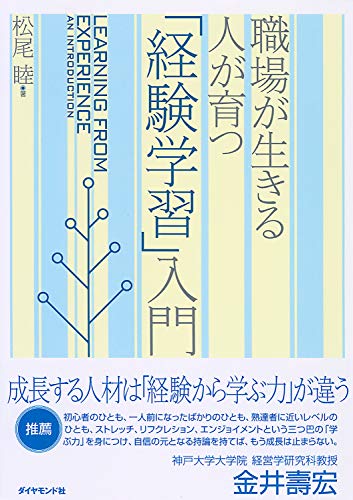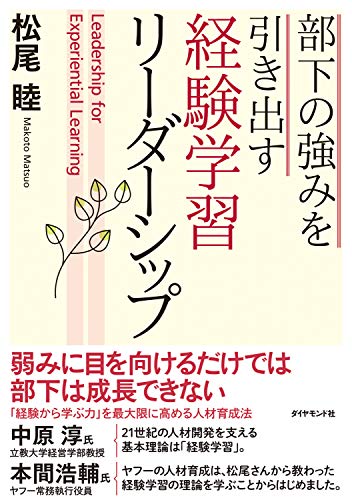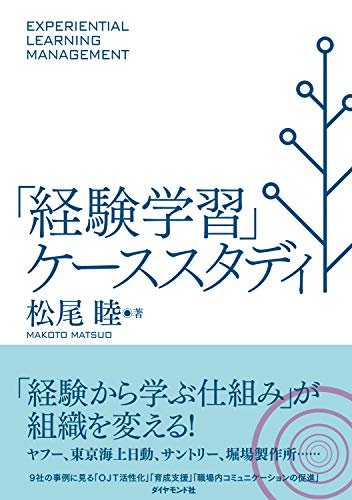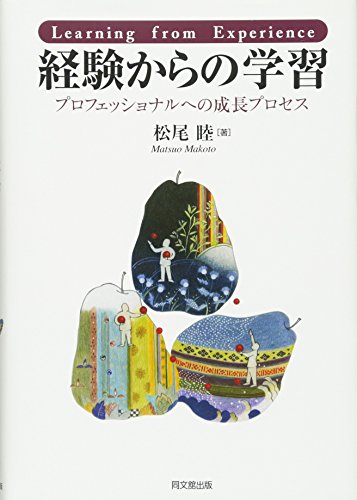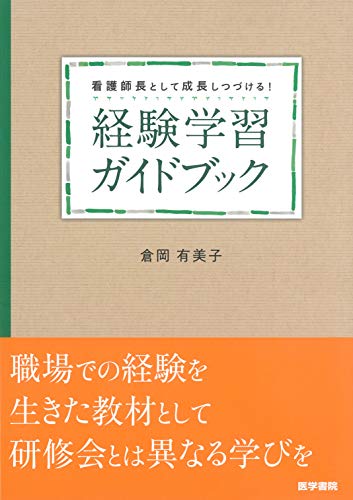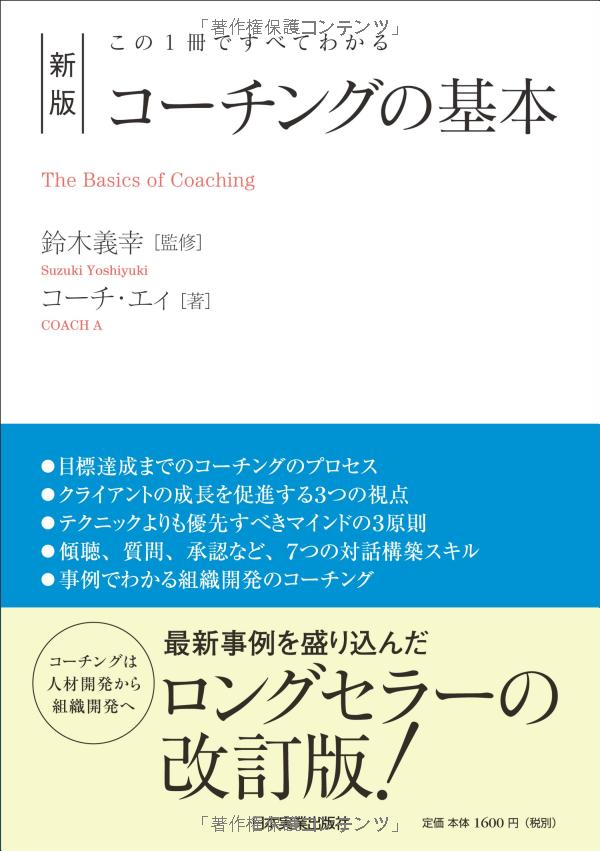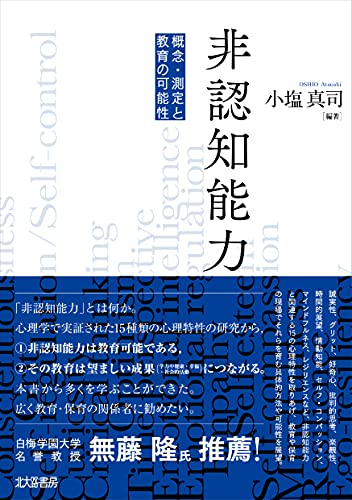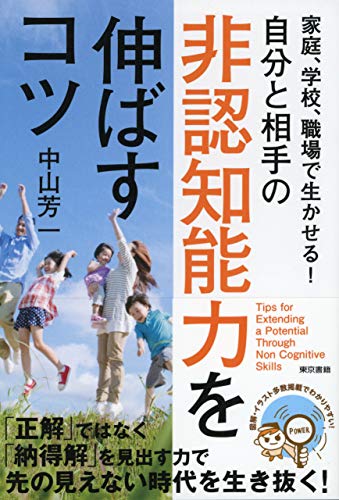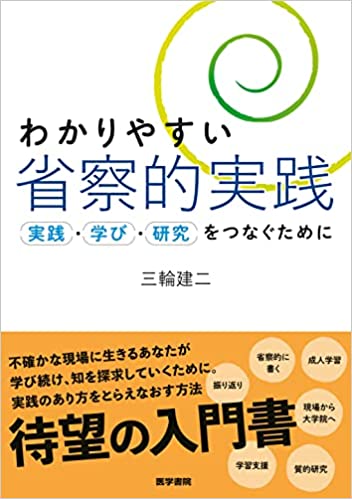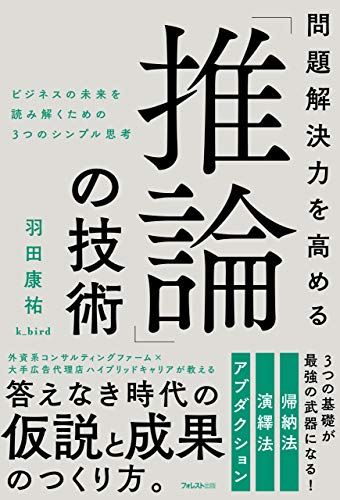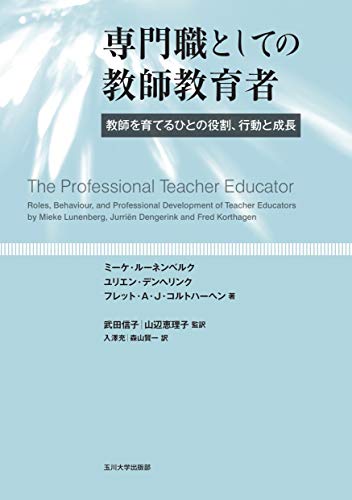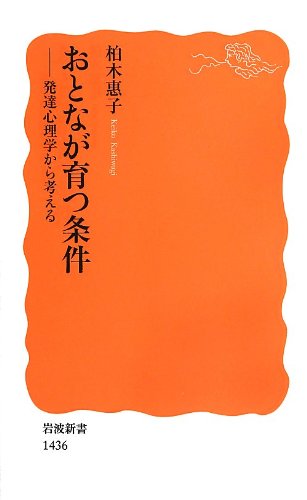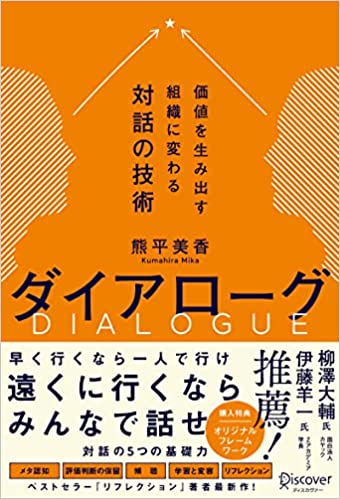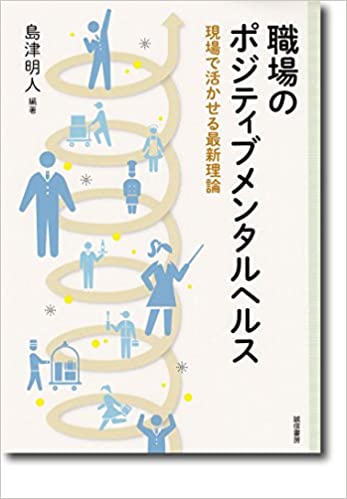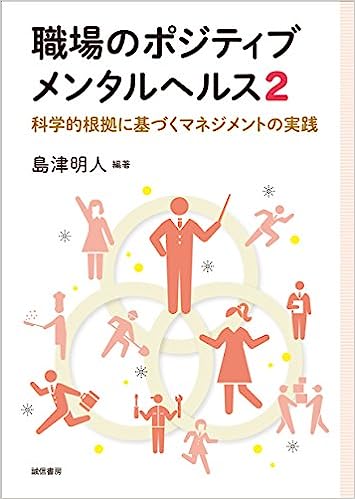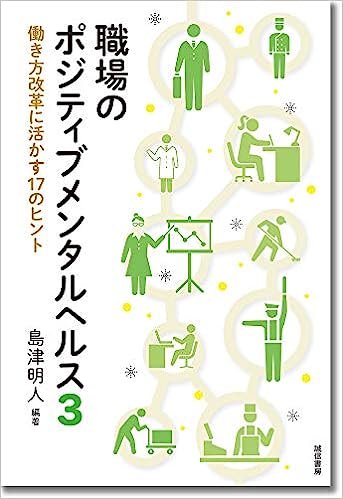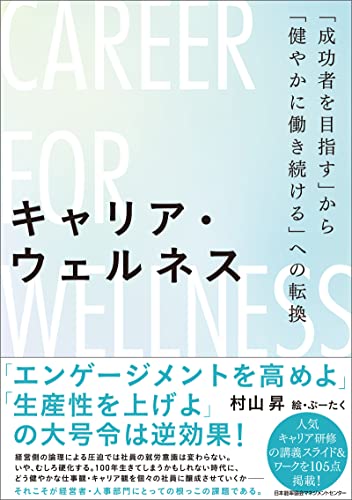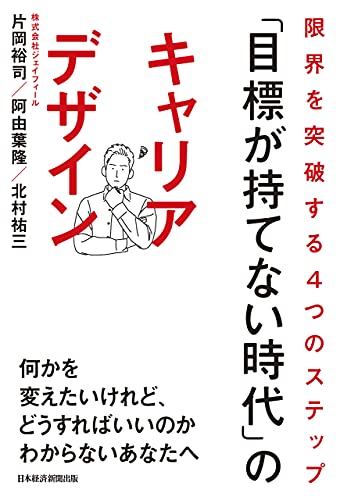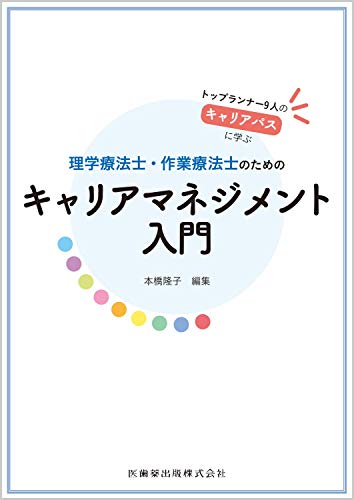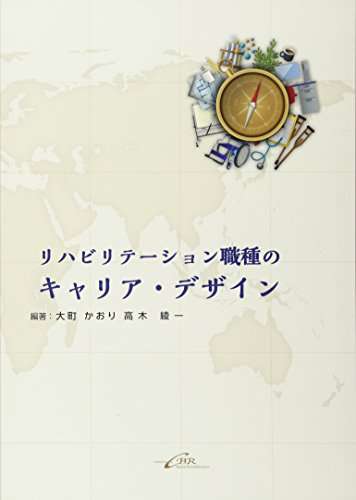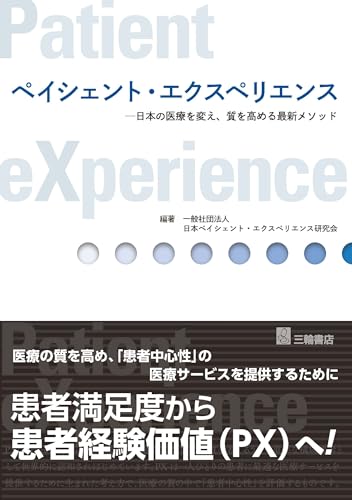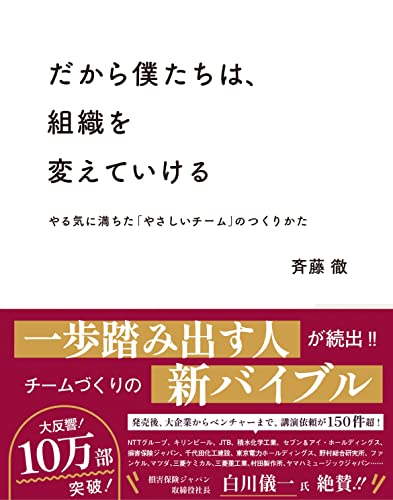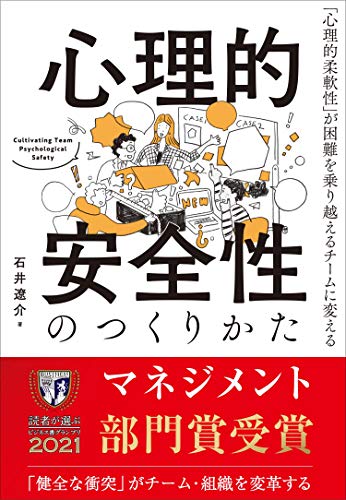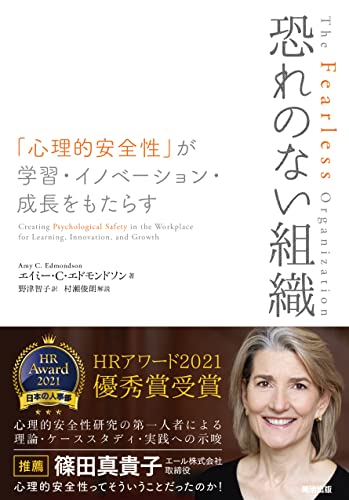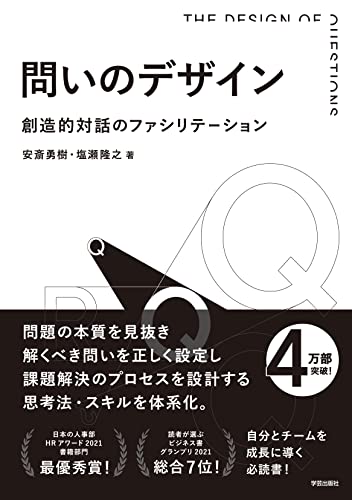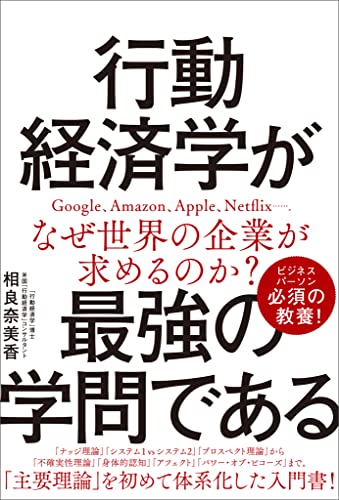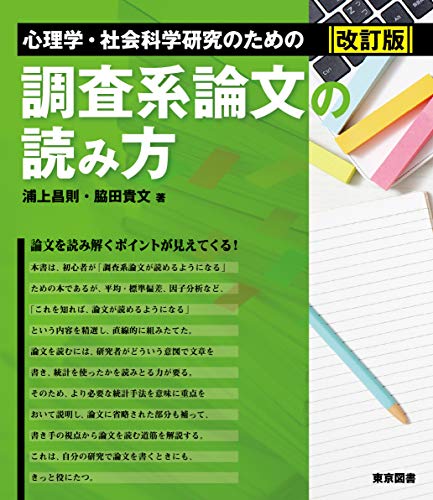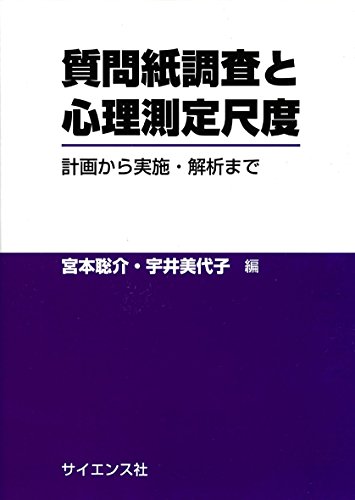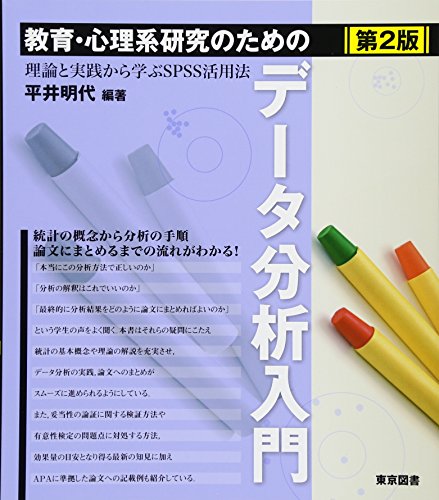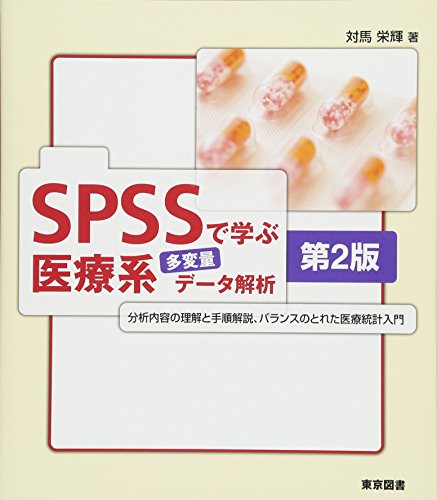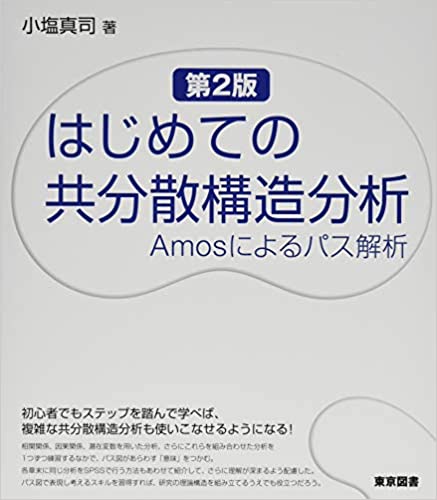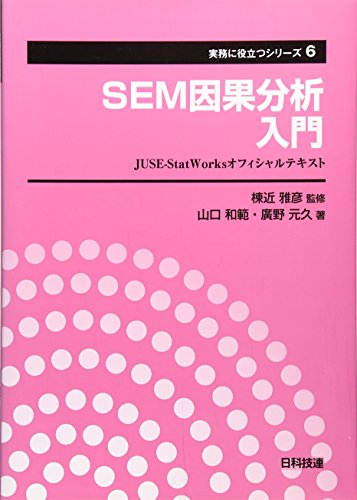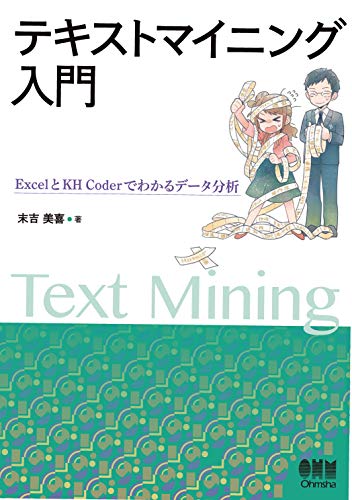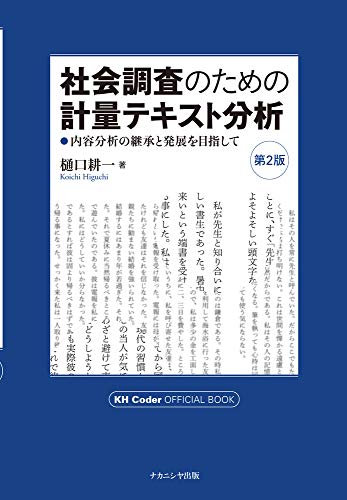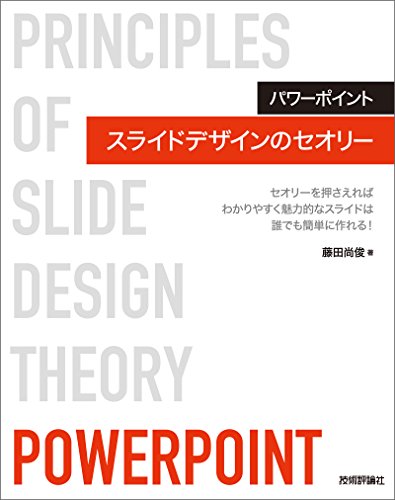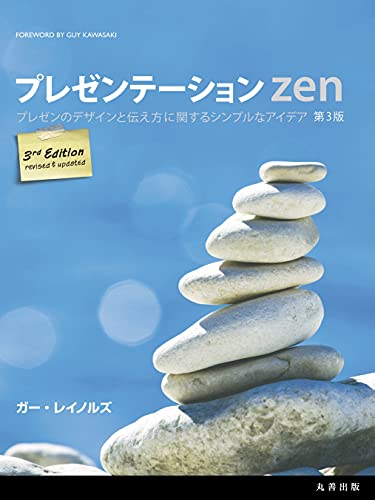書籍紹介

書籍紹介
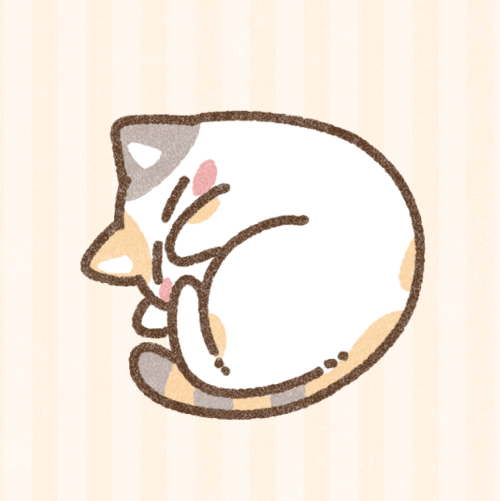
画像をクリックすると「Amazon」の購入サイトにリンクしてるよ!
「+」を押すと要約が出てくるよー
ちなみに要約はChatGPTにやってもらってます…
教育学
- リハビリテーション専門職のための教育学 現場で役立つ「教える技術」
-
教育学の専門家がリハビリテーション専門職のために理論に基づく「教える技術」をやさしく解説!
●教育学が必要なのは教員だけ?そんなことはありません。「教える技術」は臨床でも役に立つ!
●学生教育はもちろんのこと、臨床現場での人財育成まで幅広く役立つ知識が満載!
●教育学の専門家と理学療法士・作業療法士がタッグを組んで贈る、リハビリテーション専門職のための初めての教育学の本!
ポートフォリオ
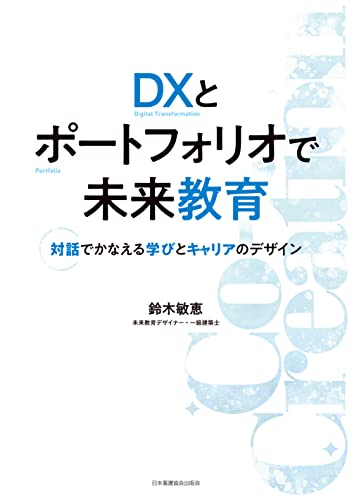


- eポートフォリオ-医学教育での意義と利用法
-
「eポートフォリオ-医療教育での意義と利用法-」は、医療教育におけるeポートフォリオの利用に焦点を当てた書籍です。eポートフォリオとは、学習者が自己評価を行い、成長の過程を記録するための電子的なポートフォリオです。
本書では、eポートフォリオが医療教育においてどのように有用であるかについて説明されています。具体的には、eポートフォリオが学習者の自己評価やフィードバック、目標設定、反省、振り返り、個人的な成長の追跡などに役立つことが紹介されています。また、eポートフォリオの利用法や導入方法についても解説されています。
さらに、本書ではeポートフォリオの実際の事例も紹介されています。例えば、eポートフォリオを使った臨床実習の評価や、eポートフォリオを活用した医療従事者のキャリア開発などが取り上げられています。
最後に、本書ではeポートフォリオを導入する上での課題や注意点、今後の展望についても触れられています。全体的に、eポートフォリオが医療教育において有用であることが示され、eポートフォリオの導入に興味がある教育者や医療従事者にとって貴重な一冊となっています。
- ポートフォリオで未来の教育 次世代の教育者・指導者のテキスト
-
「ポートフォリオで未来の教育-次世代の教育者・指導者のテキスト-」は、ポートフォリオを活用した次世代の教育者・指導者の育成について解説した書籍です。
まず、著者らはポートフォリオの概念や利用方法について説明し、ポートフォリオが学生の自己評価や自己成長を促進することや、教育者の教育指導力を高めることに役立つことを紹介しています。
次に、著者らはポートフォリオを活用した具体的な教育方法について解説しています。例えば、ポートフォリオを用いた学生の自己評価や目標設定、学生同士の評価やフィードバック、教員の指導力向上や評価制度の改善などが挙げられます。
また、著者らはポートフォリオを活用するために必要な教育者の資質や能力についても解説しています。例えば、教育者はポートフォリオの活用方法を知り、学生の自己評価や目標設定の支援、学生との対話やフィードバックの提供などを行う必要があると述べられています。
最後に、著者らはポートフォリオを活用した教育の効果について紹介しています。ポートフォリオを活用することで、学生の自己評価や自己成長意識が高まり、教育者の指導力や評価制度が改善されることが期待できると述べられています。
この書籍は、ポートフォリオを活用した次世代の教育者・指導者の育成について詳しく解説しており、教育現場でポートフォリオを活用することに興味のある方や、教育者の資質・能力向上に関心がある方にとって有益な一冊となっています。
- 教育分野におけるeポートフォリオ (教育工学選書 II)
-
教育分野におけるeポートフォリオという書籍は、教育現場においてeポートフォリオを導入することの重要性について説明し、実際にeポートフォリオを導入する際の方法や具体的な事例を紹介しています。
まず、eポートフォリオは、学習者自身が自己評価を行い、自己成長を促進するためのツールであると説明されています。また、eポートフォリオには学習者の過去の実績や成果を保存することができるため、将来の就職や進学においても役立つとされています。
次に、eポートフォリオの導入方法について説明されています。eポートフォリオを導入する際には、教育目標や評価基準を明確に設定することが重要であり、学習者が自己評価を行うための指導も必要です。また、eポートフォリオを作成するためのツールやプラットフォームの選定や、セキュリティに関する注意点も解説されています。
さらに、本書ではeポートフォリオを導入した実際の事例についても紹介されています。例えば、小学校においてeポートフォリオを導入した場合、生徒の自己評価能力や自己表現能力が向上し、学習意欲の向上にもつながったという事例が挙げられています。
最後に、eポートフォリオが教育現場においてもたらす効果について総括されています。eポートフォリオは学習者の自己評価能力や自己表現能力を向上させるだけでなく、学習成果を可視化することで教育者と学習者とのコミュニケーションを促進し、学習者の学習意欲を高めることができるとされています。
- DXとポートフォリオで未来教育: 対話でかなえる学びとキャリアのデザイン
-
DXで教育は進化する! デジタル+ポートフォリオで「意志ある学び」を実現!
教育におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か、学校教育や人材育成の場でどう実践するのかを解説するとともに、学習者の主体性・創造性を高める「ポートフォリオ」のデジタル化を具体的に提案します。
デジタル技術を活かした「ポートフォリオ・プロジェクト学習」の実践事例も多数紹介しています。【主な内容】
Part I 教育DX…時空を超えた新しい学びへ
1 教育DX—5つの未来ビジョン
2 DAOとプロジェクト社会
3 デジタル空間—ビジョンでつながるポートフォリオ
4 「新たな価値創造」を果たすプロジェクト学習
5 ポートフォリオで学びとキャリアのデザインPart II デジタル空間の[ポートフォリオ・プロジェクト学習]
1 ポートフォリオ・プロジェクト学習の基本と特徴
2 共通の学習空間は[デジタル空間]
3 デジタルポートフォリオで[思考プロセス]を評価する
4 デジタルポートフォリオの魅力と機能Part III ポートフォリオの導入と活用[未来教育シート]
1 一人ひとりがポートフォリオを持つ時代
2 ポートフォリオ導入スキーム
3 ポートフォリオ・リテラシー
4 [ポートフォリオ活用]未来教育シート
5 未来教育DX—ポートフォリオ評価Part IV オンライン教育を成功させる3つのマネジメント
1 オンライン授業を成功させる
2 [SEE図]3つのマネジメント
I 最も重要なセルフマネジメント
II 環境マネジメント
III 教育のマネジメントPart V [実践事例]教育DX…人間を大切にするプロジェクト学習
1 実践者の声
2 実践事例
自己調整学習
- 自己調整学習 主体的な学習者を育む方法と実践
-
『自己調整学習 主体的な学習者を育む方法と実践』は、学習者が自己調整学習によって自らの学習を主体的に進め、自己成長を促すための方法と実践を紹介した書籍です。
自己調整学習とは、学習者が自己評価や自己反省を通じて自らの学習プロセスを見つめ直し、必要なアクションをとることで、より効果的な学習を進める方法です。本書では、この自己調整学習の理論的背景や、実践的な方法について詳しく解説されています。
具体的には、自己評価やフィードバックの活用、目標設定や学習計画の立て方、さらには自己効力感の醸成や自己学習の習慣化など、自己調整学習を促進するための方法が紹介されています。また、自己調整学習を実践する上で必要な、教育者や指導者の役割や、学習環境の整備についても触れられています。
本書は、学習者が自己成長を促すために必要な自己調整学習の理論や実践について、分かりやすく詳しく解説された一冊です。教育現場での指導者や、自己学習を進めたい人にとって、有用な参考書となっています。
- “自己調整学習:理論と実践の新たな展開へ
-
『自己調整学習:理論と実践の新たな展開へ』は、自己調整学習に関する理論的・実践的な最新の研究成果をまとめた書籍です。
本書では、自己調整学習の基本的な理論に加え、自己調整学習に関する最新の研究成果が解説されています。具体的には、自己調整学習の対象となる学習者の特徴や、学習者の自己効力感や動機付け、学習成果の評価について、新たな知見が提供されています。
また、本書では、自己調整学習を促進するための実践的な方法についても紹介されています。具体的には、自己評価やフィードバックの活用、目標設定や学習計画の立て方、そして学習支援システムの利用など、自己調整学習を促進するための実践的な手法が取り上げられています。
本書は、自己調整学習に関する最新の研究成果や、実践的な手法について、体系的にまとめられた一冊です。教育現場での指導者や、自己学習を進めたい人にとって、自己調整学習の理解を深めるための貴重な参考書となっています。
経験学習
- 職場が生きる 人が育つ 「経験学習」入門
-
『職場が生きる 人が育つ 「経験学習」入門』は、経験学習というアプローチを用いた職場での人材育成の方法について解説した書籍です。 経験学習とは、仕事において経験を積み重ねながら自己成長を促すアプローチであり、その方法として「実践→観察→考察→実践」というサイクルを繰り返すことが重要です。このサイクルを通じて、自己成長や問題解決力、そしてリーダーシップを身につけることができます。 本書では、経験学習の理論と実践を具体的な事例を交えて解説しています。例えば、経験学習を取り入れたトレーニングプログラムの作り方や、経験学習を通じてリーダーシップを発揮する方法などが紹介されています。 また、経験学習を取り入れることで職場の環境改善にもつながるという点も強調されています。具体的には、経験学習を通じて従業員が自己成長し、より高い生産性やクオリティを実現することができるという点です。 本書は、経験学習に興味がある人や職場での人材育成に悩んでいる人にとって、非常に役立つ内容となっています。また、著者の実践的なアドバイスが多数含まれているため、実践的な視点からも非常に参考になります。
- 部下の強みを引き出す 経験学習リーダーシップ
-
『部下の強みを引き出す 経験学習リーダーシップ』は、ジョン・C・マクシウェル氏によるリーダーシップに関する書籍です。マクシウェル氏は、数多くのリーダーシップ関連書籍を著しており、リーダーシップに関する講演やセミナーを行う世界的な講演者の1人でもあります。 本書では、部下の強みを引き出すことがリーダーシップの重要な役割であるというテーマが取り上げられています。そのためには、部下の個性や能力を理解し、彼らが自分自身を成長させるための経験を提供することが必要です。本書では、経験学習と呼ばれる学習理論をベースにしたリーダーシップの手法が紹介されています。 経験学習は、新しい状況に直面した際に、過去の経験をもとに問題を解決する学習方法です。経験学習リーダーシップは、部下が自分で問題を解決できるようになるために、彼らに経験を提供することを目的としたリーダーシップの手法です。 本書では、経験学習リーダーシップの5つの段階について詳しく解説されています。まず、部下に何ができるかを見極めることが必要です。次に、部下に問題を解決する機会を与えることが必要です。その後、部下が自分で問題を解決するための支援を行い、その後、部下が成果を出した場合には称賛を与えます。最後に、部下が自己肯定感を持てるようになるようにサポートをすることが大切です。 また、本書では、経験学習リーダーシップを実践する上での具体的なアドバイスや、成功事例、失敗事例なども紹介されています。これらの情報をもとに、リーダーシップのスキルを向上させ、部下の成長を促すことができるでしょう。
- 医療プロフェッショナルの経験学習
-
最初に、経験学習の基本的な内容が簡潔にまとまっており、 その後、看護師・保健師・薬剤師・診療放射線技師・救急救命士・病院事務職員・救急救命医師・公衆衛生医師の「経験学習」による成長プロセスに関してまとまっています。各章、研究計画から結果・考察までわかりやすくまとまっており、「経験学習」についての研究の流れがわかりやすく、「経験学習」の研究を始める人には非常に参考になる一冊だと思います!!
- 「経験学習」ケーススタディ
-
松尾先生の経験学習の書籍です。大手7社の経験学習に関する経験学習について紹介されています。具体的な手法が知りたい方はおすすめです。
- 経験からの学習-プロフェッショナルへの成長プロセス-
-
「経験からの学習-プロフェッショナルへの成長プロセス-」は、個人が職業上のスキルや知識を向上させ、プロフェッショナルとして成長するための手引きです。著者は経験を通じて学び、成長するプロセスに焦点を当てています。本書では、失敗や挫折を乗り越える方法、成功体験からの学び方、そして自分の強みと弱みを理解し活かすための戦略が提示されています。読者は過去の経験を振り返り、そこから得た洞察を通じて、より優れた専門家としてのスキルを磨く手段を見つけることができます。本書は実践的なアドバイスと共に、個人の成長を促進するための洞察に満ちた一冊となっています。
- 看護師長として成長しつづける! 経験学習ガイドブック
-
「看護師長として成長しつづける! 経験学習ガイドブック」は、看護師長がキャリアを築き、成長し続けるための実践的なガイドです。本書では、経験学習を通じて看護師長が専門的なスキルやリーダーシップ能力を向上させる方法が探求されています。著者は失敗や成功からの学び方、仕事とプライベートのバランスの取り方、そして組織内でのコミュニケーションの重要性などに焦点を当てています。また、臨床現場や組織運営における課題にどのように取り組むかについても実践的なアドバイスが提供されています。本書は看護師長が持つべきスキルや資質について理解を深め、自らの成長を促進する手助けとなるでしょう。経験を通じた学びと実践を通して、看護師長としての専門性を高め、職務においてリーダーシップを発揮するための知識が凝縮された一冊です。
コーチング
- この1冊ですべてわかる 新版 コーチングの基本
-
「この1冊ですべてわかる 新版 コーチングの基本」は、コーチングの基礎を網羅した書籍です。コーチングは、人々が目標を達成し、成長するための支援手法であり、本書ではそのエッセンスを解説しています。 本書では、コーチングの定義や基本原則について詳しく説明されています。コーチングの目的や価値観、コーチとクライアントの関係性の構築方法など、基本的な概念を理解するのに役立ちます。 さらに、本書では実践的なコーチングの手法やフレームワークも解説されています。コーチングセッションの進め方や質問のテクニック、目標設定や行動計画の立て方など、具体的なスキルやツールが紹介されています。 また、本書ではコーチングの応用範囲にも触れています。ビジネスや組織の中でのコーチングの活用方法や、個人の成長やキャリアの支援におけるコーチングの重要性についても解説されています。 「この1冊ですべてわかる 新版 コーチングの基本」は、初心者から経験者まで幅広い読者に役立つ一冊です。コーチングの基礎知識を学びたい人や、自己成長や他者支援に興味のある人にとって、理解しやすい内容となっています。
- コーチング・バイブル(第4版)―人の潜在力を引き出す協働的コミュニケーション
-
「コーチング・バイブル(第4版)」は、協働的なコミュニケーションを通じて人々の潜在力を引き出すコーチングのアプローチに焦点を当てた本です。著者はコーチングが単なるスキルやテクニックではなく、相手との共感と連携に基づく協力的なプロセスであると強調しています。本書では、コーチングの基本的な原則やスキル、具体的な手法について解説されています。著者は、質問の仕方、リスニングの重要性、フィードバックの提供など、コーチングにおけるコミュニケーションの要素に焦点を当て、実践的なアプローチを読者に提供しています。
また、コーチングのプロセスにおいてクライアントとの協力関係を構築し、目標の明確化や成果の測定方法についても触れています。著者は、コーチングがリーダーシップや組織内のコミュニケーション改善にも応用できると説明し、コーチングが個人や組織の発展に寄与する方法を示唆しています。
この本は、コーチングを深化させ、人々の成長や目標達成に向けてコミュニケーションをより効果的に活用したいと考える人々に向けた実践的なガイドとなっています。
非認知能力
- 非認知能力: 概念・測定と教育の可能性
-
『非認知能力: 概念・測定と教育の可能性』は、教育において認知能力だけでなく、非認知能力も重要であることを論じた書籍です。著者は、非認知能力とは、人間の行動・思考において認知的なスキルや知識以外に必要とされる、感情・動機づけ・社会的関係などの力を指すと定義しています。 本書では、非認知能力の様々な側面について詳しく説明し、その重要性を論じます。例えば、グリットという概念は、目標設定・忍耐力・自己規律などの能力を含み、成功において重要な役割を果たすことがわかっています。また、自己効力感や希望といった概念も、人々が問題に取り組む意欲や成功するための意志力を高める上で重要な役割を担っています。 本書ではさらに、非認知能力の測定方法や教育における取り組みについても説明されています。著者は、非認知能力を測定するための様々なツールが存在することを紹介し、教育現場で非認知能力を向上させるための方法についても提案しています。例えば、授業内での自己規律や協調性を促す活動や、生徒が自分の目標を設定し、それを達成するための支援をすることが重要だと述べられています。 本書は、非認知能力が教育において重要であることを訴え、その測定方法や教育における取り組みについて具体的な提案をしています。教育現場で非認知能力を向上させることが、生徒たちの成功につながるという点を強調しています。
- 家庭、学校、職場で生かせる!自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ
-
「家庭、学校、職場で生かせる!自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ」は、非認知能力の重要性に焦点を当て、その向上を促進する方法を提案する本です。著者は家庭、学校、職場といった異なる環境で非認知能力を伸ばすための具体的なアプローチを示しています。
本書では、非認知能力とは感情の管理、人間関係の構築、自己管理といった、学業や仕事の成功において重要なスキルを指すと説明されています。これらの能力は、単なる知識やIQだけでなく、個人の総合的な成長や生涯の成功にも影響を与えるとされています。
著者は、非認知能力を育むための方法として、感謝の実践、ポジティブなコミュニケーション、目標の設定と追求などの手法を紹介しています。これらのスキルは家庭環境や学校、仕事の場で学び、実践することで向上すると説明されています。
この本は、非認知能力を伸ばし、個人やチームのパフォーマンス向上に寄与するための実践的なヒントとアイディアを提供しています。読者は日常生活でこれらの原則を活用し、自己および他者の非認知能力の向上に取り組むことができます。
内省(リフレクション)
- わかりやすい省察的実践 実践・学び・研究をつなぐために
-
「わかりやすい省察的実践」は、実践的に省察を行う方法を紹介するビジネス書です。著者の佐々木正幸氏は、自己変革や組織変革に取り組む人々を対象に、省察という手法を使って課題解決をすることの重要性を説いています。
本書では、省察の定義と方法論を解説します。省察とは、考え事を深く考えることで、現状を客観的に見極め、これからの方策を見出すことを指します。省察の方法には、問いかけや対話、メモの取り方などの具体的な手法が紹介されています。
また、本書では、省察によって見つかった課題を解決するためのアプローチについても解説されています。課題解決には、問題整理や仮設検証など、プロセスに沿って一歩ずつ進めていく方法が推奨されています。
そして、省察的実践を行うためには、クリアな目標設定が必要不可欠です。目標設定には、SMARTの原則を用いるなどの指南もされています。
このように、本書では、省察の概念、方法、実践について丁寧な解説がされています。課題解決に取り組む上で省察を使い、問題を明確にし、着実に解決していくことができるため、自己変革や組織変革に取り組むビジネスマンには必読の書と言えます。
“わかりやすい省察的実践わかりやすい省察的実践わかりやすい省察的実践”へメッセージを送信
- リフレクション(REFLECTION) 自分とチームの成長を加速させる内省の技術
-
「リフレクション(REFLECTION) 自分とチームの成長を加速させる内省の技術」は、個人およびチームの成長を促進するための内省の重要性に焦点を当てた本です。著者はリフレクション(内省)を通じて自己理解を深め、プロフェッショナルとしてのスキルを高める手法を提案しています。本書では、日常の経験や仕事において起きた出来事を振り返り、そこから得られる学びを引き出す方法や、チームとしての協力と成長を促進する手法について具体的なガイドが提供されています。著者は、リーダーシップ、コミュニケーション、問題解決などの側面でリフレクションがどれほど効果的かを強調し、読者が日常の経験を通じて自分やチームを向上させるための具体的なステップを示しています。本書は、個人とチームが継続的に学び、発展し続けるための実践的なアプローチを提供しています。
成人学習論
- 成人学習者とは何か―見過ごされてきた人たち
-
「成人学習者とは何か―見過ごされてきた人たち」は、成人学習者に焦点を当て、彼らが教育プロセスにおいてどのように理解され、支援されるべきかについての本です。著者は従来の教育の中で成人学習者が適切な評価や支援を受けられていないことに注目し、その理由や解決策について探求しています。
本書では、成人学習者の特徴、学習スタイル、生活経験の影響などに焦点を当てながら、彼らが持つ潜在能力や学びたいという欲求にスポットを当てています。著者は、成人学習者が異なるバックグラウンドやニーズを持っており、それに対応するためには教育の柔軟性や個別化が求められると強調しています。
また、成人学習者が学びの機会を得るためには、教育機関や指導者が彼らの多様性を理解し、それに基づいたサポートを提供する必要があると述べています。著者は、成人学習者を無視することなく、教育環境をより包括的かつ包括的にするための提案や洞察を提供しています。
EBM教育
- EBM:根拠に基づく医療
-
「根拠に基づく医療(EBM)」の実践と指導法の世界的スタンダードの翻訳版。
これからの医療者の育成に必携の一冊!!本書は、臨床家や医学教育関係者を対象にした「Evidence-Based Medicine : How to Practice and Teach EBM , Fifth Edition」の日本語翻訳版です。
根拠に基づく医療(EBM)の実践と教育を志す臨床医のために書かれた、スタンダード・テキストです。EBMの直接的な臨床応用と、EBMを実践・指導するための方策に力点を置いた、簡潔で実用的な内容となっています。
思考法・学習法
- 問題解決力を高める「推論」の技術
-
力を高めるための具体的な方法や練習方法が紹介されています。推論とは、ある事実や情報から別の事実や情報を導き出す能力のことであり、日常生活やビジネスにおいて重要なスキルの一つです。本書では、推論力を高めるために必要な3つの要素である「知識・観察・練習」について詳しく解説されています。 まず、推論力を高めるためには豊富な知識が必要です。本書では、様々な分野から身につけた知識を使って、推論力を養う方法が紹介されています。また、観察力は推論力養成に欠かせないもう一つの要素です。観察力を高めるためには、あらゆる情報に興味を持ち、自分なりの視点で見ることが大切です。そして、推論力を高めるための練習方法も紹介されています。例えば、日常生活で起こった出来事を思い出し、その原因や結果を想像するトレーニングなどが紹介されています。 本書では、推論力を高めるために必要な要素だけでなく、推論力が高まるとどのようなメリットがあるかにも触れています。例えば、ビジネスの現場では、顧客の要望やニーズを推論できることが重要です。また、課題解決においても、推論に基づいたアプローチは効果的な解決策を導くことができます。 本書は、ビジネスシーンにおける問題解決に必要なスキルである推論力を、初心者から上級者まで幅広くカバーした実践的な書籍です。豊富な例や実践的な練習方法などが掲載されており、今後推論力を鍛えたいと考えている人におすすめの一冊です。
- 進化する勉強法:漢字学習から算数、英語、プログラミングまで
-
「進化する勉強法:漢字学習から算数、英語、プログラミングまで」は、多岐にわたる学習領域において進化する勉強法を提案する本です。著者は漢字学習から算数、英語、プログラミングまで、異なる分野に対する効果的な学習戦略を紹介しています。本書では、漢字学習においては単なる覚え方ではなく、ストーリー化やイメージングを組み合わせることで効果的な記憶法を提案しています。算数や英語においては、問題解決やコミュニケーションスキルの向上に焦点を当てながら、実践的で興味深いアプローチが提示されています。
また、プログラミングの学習においては、単なるコードの書き方だけでなく、プロジェクトを通じた実践的なスキル構築が強調されています。独自の学習プランやリソースの活用方法も提案され、読者が自己成長を促進する手助けとなるでしょう。
この本は単なる暗記や単語覚えだけでなく、深い理解と実践的なアプローチを組み合わせ、学習をより意味のあるものにするための手法を提供しています。
教師教育学
- 教師教育学:理論と実践をつなぐリアリスティック・アプローチ
-
タイトルの通り、専門職としての教師教育者とは何か?について約20年分の論文をレビューして解説してくれています。 生徒に教えるために指導者に教えるべきことの研究は進んでいますが、教師を教育する手法に関しては十分に検討されておらず、ここ20年で論文が増えてきたまだまだ未熟な分野です。 リハビリ分野においても、指導者を育てる上で重要なことが多く書いています。
- 専門職としての教師教育者 ―教師を育てるひとの役割、行動と成長―
-
教師教育学の第一人者である著者陣が、教師教育者の働き方、成長の仕方、知識と能力のあり方、学びの支援の方法など、過去20年間における各国の教師教育者の専門性開発に関する先行研究を網羅的にまとめ、その意義を読み解く。付録には重要な先行研究をリスト化。今後の日本での教師教育研究を方向づける重要な書。
- おとなが育つ条件――発達心理学から考える
-
「おとなが育つ条件――発達心理学から考える」は、発達心理学の視点から成人期における発達とその条件を考察する本です。著者は、成人期の発達について理解し、個々の人が豊かな人生を築くための条件を探求しています。
本書では、人は生涯にわたって発達し続ける存在であるという発想に焦点を当てています。著者は、仕事、家庭、人間関係など様々な側面での成人期の課題や変化について具体的な事例を交えながら解説しています。成人期における心の変化や対人関係の重要性などが掘り下げられています。
また、本書では自己認識や自己成熟、人間関係におけるコミュニケーションスキルの向上など、成人期における発達を促進するための要因にも触れています。著者は、読者に対して発達心理学の理論を通じて自己理解を深め、より健全で満足のいく人生を築くためのヒントを提供しています。
管理学
リーダーシップ
- リーダーシップの理論
-
「理論は難しくて理解しづらい」?
「理論など現場では役に立たない」?難しいと思われがちな理論は、
実はわかりやすく、
面白く、実務の役に立つ!
経験や勘に加えて「理論」という武器をもち、
応用力のあるリーダーシップを発揮できるようになる1冊。最新の理論はもちろん,
時代の変化に合わせて発展してきた
理論の流れにそってわかりやすく解説。
- 世界最高のリーダーシップ 「個の力」を最大化し、組織を成功に向かわせる技術
-
全米ベストセラー、満を持して日本上陸。ウーバー、ライアットゲームズ、WeWorkなどを次々再生したハーバード・ビジネススクール教授による、古今東西の叡智を結集した「最高のリーダーシップ」。リーダーシップは簡単ではない。あきらめない強い心、勇気、ビジョンをはじめ、さまざまな資質が必要だ。厳しい状況でそれらの資質を発揮するのは難しい。リーダーや、リーダーを目指す人がアドバイスを求めると、たいてい「もっとがんばれ」、「もっと深堀りしろ」という答えが返ってくる。鏡に映る自分を見て、生まれながらの強みを生かし、そして足りない部分を補えばいい、と。フランシス・フライとアン・モリスは違う世界観を提供する。2人の主張によると、こういった一般的なリーダーシップ論では、リーダーにとってもっとも大切な仕事が隠されてしまうという。その仕事とは、他者(メンバー)を育てることだ。リーダーシップの主役はあなたではない。メンバーをどれだけ効果的にエンパワーできるかがリーダーシップの本質だ――そして、その影響力を、あなたがその場にいなくなってからも永続させなければならない。フライとモリスは、古代ローマから現代のシリコンバレーまで、古今東西の刺激的な物語を提示する。そこから見えてくるのは、偉大なリーダーシップの源泉だ。逆説的に聞こえるかもしれないが、偉大なリーダーシップに、リーダー自身の地位や出世は関係ない。大切なのは、メンバーの潜在能力に徹底的にフォーカスする姿勢だ。『Unleashed』は、現代のリーダーシップの実践に役立つ画期的なアドバイスを提供する。もっとも大胆で、もっとも効果的なリーダーに共通するのは、信頼、愛、帰属という特別な組み合わせを活用し、メンバーが最高の能力を発揮できる環境を整えていることだ。フライとモリスが伝授するツールは、すでに現場で試されて効果が証明されている。ウーバー、ライアットゲームズ、WeWorkといった企業と働いた経験から生まれたツールだ。そこに当事者へのインタビューや、著者たちの個人的な経験談も加わり、アイデアがより説得力を持って読者に迫ってくる。他者の中に眠る偉大さを解き放ちたいのなら、この本が欠かせないガイドになるだろう。そして究極的に、あなた自身の中に眠る偉大さも解き放たれることになる。(原著紹介文より)
コミュニケーション
- 保健医療専門職のためのヘルスコミュニケーション学入門
-
「保健医療専門職のためのヘルスコミュニケーション学入門」は、保健医療の専門家を対象とした、ヘルスコミュニケーションに焦点を当てた入門書です。著者はコミュニケーションスキルが患者との関係構築や情報伝達において極めて重要であると認識し、その理解を深めるための手引きを提供しています。本書では、患者とのコミュニケーションにおいて臨床的効果を向上させるための基本的な原則や技術に焦点を当てています。感情の理解、非言語コミュニケーション、共有意思決定の重要性などが具体的な事例を通じて解説されています。
また、情報伝達だけでなく、保健教育や予防プログラムにおいてもコミュニケーションが鍵となることを強調しており、専門職が個別の患者との関係だけでなく、コミュニティ全体に向けたメッセージの効果的な伝達にも焦点を当てています。
病態理解、治療法の知識だけでなく、コミュニケーションスキルの向上が総合的な患者ケアの一環となることを理解するための手助けとなる一冊です。
- ダイアローグ 価値を生み出す組織に変わる対話の技術
-
「ダイアローグ 価値を生み出す組織に変わる対話の技術」は、デビッド・ボールドウィン著のビジネス書です。本書では、組織の問題解決やチームビルディングにおいて、対話の力を活用することが重要であると主張しています。 本書では、対話の重要性について詳しく説明した上で、対話を行う上での技術やコツを紹介しています。さらに、対話を通じてどのように組織やチームが変わっていくかについても解説しています。 本書の中では、対話にはいくつかの種類があり、それぞれの種類に応じた対話の方法やスキルが必要であると説明されています。また、対話においては相手への理解や共感が重要であるため、相手の感情に寄り添うことが大切であると述べられています。 本書では、対話を通じて組織やチームが変わっていく様子を具体的な事例を交えて解説しています。例えば、対話によってメンバー間の信頼関係が築かれ、意見の違いや問題を共有することができるようになり、組織の成果が向上するといった具合です。 また、本書では、対話を通じて組織が持つべき価値観や目的を明確にすることが重要であると述べられています。これによって、組織全体が共通の目標に向かって協力することが可能になります。 本書を読むことで、対話を活用することで組織やチームがより良く機能し、価値を生み出すことができるようになるためのノウハウが学べます。組織開発やリーダーシップに興味のある人におすすめの書籍です。
ワーク・エンゲージメント
- 新版 ワーク・エンゲイジメント
-
「ワーク・エンゲージメント – 基本理論と研究のためのハンドブック」は、ワーク・エンゲージメントについての最新の理論や研究成果をまとめた専門書です。以下は、書籍の主な内容を要約したものです。 ワーク・エンゲージメントとは、労働者が自分の仕事に対して高い関心や熱意、満足感を持って取り組むことを指します。ワーク・エンゲージメントは、労働者の生産性や組織の成果に直結する重要な要素であり、現代の労働環境においてますます注目されています。 本書では、ワーク・エンゲージメントの定義や測定方法、関連する理論、影響要因、効果などについて詳しく解説されています。また、組織のマネジメントやリーダーシップ、社員のキャリア開発、労働環境の改善など、ワーク・エンゲージメントを促進するための具体的な手段や戦略についても紹介されています。 さらに、本書では、ワーク・エンゲージメントが組織の成果に与える影響や、組織外部との関係、社会的責任など、より広い視野からのアプローチも紹介されています。これらの情報は、組織のマネジメントや人事部門、コンサルタント、研究者など、様々な関係者にとって役立つことでしょう。 総合的に見ると、「ワーク・エンゲージメント – 基本理論と研究のためのハンドブック」は、ワーク・エンゲージメントに関する包括的な情報を提供する、専門的で高度な書籍といえます。
- ワーク・エンゲイジメント-基本理論と研究のためのハンドブック
-
「ワーク・エンゲージメント – 基本理論と研究のためのハンドブック」は、ワーク・エンゲージメントについての最新の理論や研究成果をまとめた専門書です。以下は、書籍の主な内容を要約したものです。 ワーク・エンゲージメントとは、労働者が自分の仕事に対して高い関心や熱意、満足感を持って取り組むことを指します。ワーク・エンゲージメントは、労働者の生産性や組織の成果に直結する重要な要素であり、現代の労働環境においてますます注目されています。 本書では、ワーク・エンゲージメントの定義や測定方法、関連する理論、影響要因、効果などについて詳しく解説されています。また、組織のマネジメントやリーダーシップ、社員のキャリア開発、労働環境の改善など、ワーク・エンゲージメントを促進するための具体的な手段や戦略についても紹介されています。 さらに、本書では、ワーク・エンゲージメントが組織の成果に与える影響や、組織外部との関係、社会的責任など、より広い視野からのアプローチも紹介されています。これらの情報は、組織のマネジメントや人事部門、コンサルタント、研究者など、様々な関係者にとって役立つことでしょう。 総合的に見ると、「ワーク・エンゲージメント – 基本理論と研究のためのハンドブック」は、ワーク・エンゲージメントに関する包括的な情報を提供する、専門的で高度な書籍といえます。
ジョブ・クラフティング
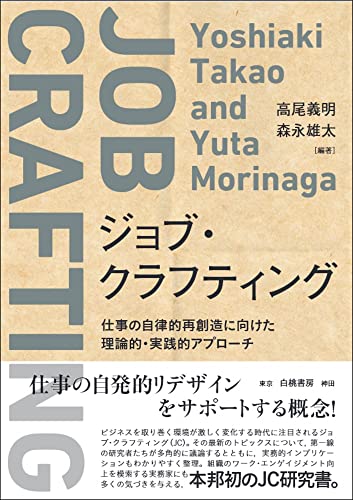


- ジョブ・クラフティング: 仕事の自律的再創造に向けた理論的・実践的アプローチ
-
ジョブ・クラフティングに関して、論文をレビューしてくれていて、今日に至るまでの歴史、各理論の利点・問題点・今後の課題が体系的にまとまっています。 この分野で研究する人は、まずこの書籍を読むのはいいのではないでしょうか? …ただ難解です。
メンタリング
- 職場のポジティブメンタルヘルス:現場で活かせる最新理論
-
- 「職場のポジティブメンタルヘルス:現場で活かせる最新理論」は、職場におけるポジティブなメンタルヘルスの促進に役立つ最新の理論と実践的な手法に焦点を当てた書籍です。 この本では、従業員の心理的な幸福感や健康状態を向上させるための概念や戦略について詳しく説明されています。具体的には、以下のような要点が取り上げられています: ポジティブ心理学の応用:ポジティブ心理学の原則やツールを職場に応用する方法について解説されています。従業員の自己成長や目標設定、ポジティブな感情や思考の促進など、ポジティブ心理学の理論を活用することで職場のメンタルヘルスを向上させることができます。 心理的安全性の醸成:従業員が意見や感情を自由に表明できる心理的に安全な環境を作り出すための方法が紹介されています。上司や同僚とのオープンなコミュニケーションや信頼関係の構築、フィードバックの文化の導入などが取り上げられています。 働き方の改革:柔軟な働き方やワークライフバランスの尊重、ストレス管理の取り組みなど、働き方を改善するための戦略が提案されています。仕事とプライベートの調和を図るための制度やリソースの提供が重要であり、そのための具体的な手法が紹介されています。 この書籍は、最新の研究や理論を基にした実践的なアドバイスや具体例を通じて、職場のポジティブメンタルヘルスの向上に貢献するための貴重な情報源となるでしょう。
“職場のポジティブメンタルヘルス:現場で活かせる最新理論”へメッセージを送信
- 職場のポジティブメンタルヘルス2: 科学的根拠に基づくマネジメントの実践
-
『職場のポジティブメンタルヘルス2:科学的根拠に基づくマネジメントの実践』は、職場における労働者のメンタルヘルスを改善し、生産性や業績を向上させる方法を科学的に解説する書籍である。 本書は、著者の数名が長年の研究・実践をもとに、職場の不安やストレス、不満を軽減するマネジメント方法を提供している。まず、職場のメンタルヘルスを改善するためには、経営層からのサポートが不可欠であることを説明し、上層部が働き手に対して、セミナーやカウンセリングなどを利用した精神保健サービスを提供するよう指導することが必要との立場を提示する。 また、本書では、組織内のコミュニケーションの重要性も強調している。マネジャーと従業員との間によい関係があることで、従業員のストレスやプレッシャーを軽減することができるとアドバイスを提供し、それによって職場のパフォーマンスの向上を期待するように促している。本書では、従業員が肯定的なフィードバックを与えたり、積極的な声援を送ったりするためのコミュニケーションスキルを学ぶことが重要だと説明している。職場の文化や改善のための具体的な方法論を紹介するなど、実践的なtipsも盛り込まれた一冊である。
- 職場のポジティブメンタルヘルス3:働き方改革に活かす17のヒント
-
「職場のポジティブメンタルヘルス3: 働き方改革に活かす17のヒント」は、職場におけるポジティブなメンタルヘルスを促進するための17のヒントを提供する書籍です。
この本は、現代の働き方改革の背景を踏まえ、職場の環境と従業員のメンタルヘルスの関係性に焦点を当てています。著者は、健康で生産的な職場環境を構築するために必要な要素を明確にし、実践的なアドバイスを提供しています。
本書では、以下のような17のヒントが紹介されています:
メンタルヘルスの重要性を認識する
コミュニケーションを改善する
ストレス管理の戦略を導入する
ワークライフバランスを促進する
チームの協力とサポートを強化する
リーダーシップの役割を強化する
セルフケアを重視する
フレキシブルな働き方を採用する
プロフェッショナルな成長とスキル開発をサポートする
ポジティブなフィードバックを提供する
仕事の負荷を適切に管理する
チームビルディングの活動を実施する
インクルーシブな職場文化を促進する
ライフスキルトレーニングを提供する
リモートワークの挑戦に対処する
カウンセリングやサポートサービスを提供する
ポジティブな組織文化を構築する
これらのヒントは、従業員のメンタルヘルスを向上させ、職場のパフォーマンスと満足度を高めるための具体的な手法やアイデアを提供しています。読者はこれらのヒントを実践し、より健康で幸福な職場環境を構築することができます。
キャリア
- キャリア・ウェルネス 「成功者を目指す」から「健やかに働き続ける」への転換
-
「健やかに」働き続けるにはキーワードに、キャリアをどう積み重ねてていくことが必要かが書かれています。 講義用のスライドが記載されており、視覚的にもわかりやすい書籍です。
- 「目標が持てない時代」のキャリアデザイン 限界を突破する4つのステップ
-
何かを変えたいけれど、
どうすればいいのかわからない……
新人から中堅、ベテランまで全てのビジネスパーソンへ。ワクワクする働き方が見つかる、
想像以上の自分に出会える。
新しいキャリアデザインの方法論。事例も満載。
副業、社内起業、転職、
パラレルキャリア、独立……働き方は1つじゃない!
- リハビリテーション職種のキャリア・デザイン
-
資格があっても仕事が無い?!
これからの将来、リハビリテーション職種=PT・OT・STの雇用は不安定になり、労働市場において極めて熾烈な競争を強いられることになります。近い将来に生じるPT・OTの過剰供給、地域包括ケアシステムの推進、高齢者数の増加の頭打ち、ロボットテクノロジーなどの技術革新、国家財政のひっ迫等が、リハビリテーション職種に熾烈な競争を強いる原因となります。不確かな時代の中で、不安を感じているリハビリテーション職種の方は少なくありません。
「長い将来、この仕事をやっていけるのか?」
「将来に漫然とした不安がある」
「自分がやりたいことがみつからない…」将来の自分を思い描けていますか?
現代は、全てのリハビリテーション職種にとってキャリア開発の視点が
不可欠な時代といえます。
リハビリテーション職種を目指す学生・若手が自分に向き合い、
自分の人生を切り開くためのキャリア・デザインの方法論をわかりやすく解説します。
患者経験価値(PX)
- ペイシェント・エクスペリエンス─日本の医療を変え、質を高める最新メソッド
-
医療の質を高め、「患者中心の医療」を提供するにはどうするか。日本の医療機関ではこれまで、患者中心性を評価する手段として患者満足度を用いてきた。しかし昨今、患者の「経験」を測定する「患者経験価値(PX)」が、欧米を中心に注目されてきている。一人ひとりの患者に最適な医療サービスを提供するために生まれた考え方、PX。本書は日本初のPX研究・推進団体である日本ペイシェント・エクスペリエンス研究会によるPXの解説書にして実践集である。
感情労働
- 感情労働マネジメント 対人サービスで働く人々の組織的支援
-
『感情労働マネジメント 対人サービスで働く人々の組織的支援』は、対人サービスに従事する人々が抱える感情労働の負担を軽減するための組織的支援について解説した書籍です。著者の伊藤昌子氏は、感情労働に関する研究を行っており、企業や団体でのセミナーやコンサルティング活動を行っています。 本書では、感情労働とは何か、その負担が対人サービスに従事する人々にどのような影響を与えるかについて詳しく解説されています。また、組織的支援の必要性や、具体的な支援策についても解説されています。 感情労働とは、職業上の義務や期待に基づき、感情の表現や抑制が求められる労働のことを指します。例えば、接客業や医療業界、教育業界などでの顕著なものです。この感情労働には、ストレスや心身の負担が伴うことが多く、うつ病や不眠症、ストレス障害などの原因にもなります。 感情労働に従事する人々にとって、組織的支援は非常に重要です。本書では、具体的な支援策として、職場内のコミュニケーションの改善、ストレスマネジメントの取り組み、個人のセルフケアの重要性などが紹介されています。また、組織としてのサポートを受けるだけでなく、個人としても自己管理やコミュニケーションスキルの向上が求められます。 本書は、感情労働をテーマにした書籍の中でも、組織的支援の観点から非常に具体的なアドバイスを提供しています。対人サービスに従事する人々だけでなく、リーダーや人事担当者など、組織運営に関わる全ての人々にとって役立つ一冊と言えます。
心理的安全性
- だから僕たちは、組織を変えていける ―やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた
-
『だから僕たちは、組織を変えていける ―やる気に満ちた「やさしいチーム」のつくりかた』は、組織内で働く人々が「やる気に満ちたやさしいチーム」をつくり、組織をよりよい方向へ導くためのアドバイスを提供する書籍です。
著者は、組織の中で働く人々が仕事にやりがいを感じ、自発的に行動することができる「やる気に満ちたチーム」をつくるためには、以下の3つの要素が重要であると説明しています。
やさしさと共感
チーム内の人々が互いに理解し、支え合い、心地よい関係を築くことが重要です。仕事とプライベートのバランスをとり、メンバーが相手のことを思いやり、共感できるようなコミュニケーションを心がけることが必要です。目的意識と共有
チームメンバーが共通の目標に向かって取り組むことが重要です。目標が明確であり、全員が共有し、その達成に向けて協力することが必要です。自律性と責任
チームメンバーが自己管理能力を持ち、自ら判断して行動することが重要です。自分の責任と役割をしっかりと理解し、その達成に向けて自主的に行動することが必要です。このような要素を実践することで、組織内で働く人々が「やる気に満ちたやさしいチーム」をつくり、組織をよりよい方向へ導くことができます。著者は、このようなアプローチが組織の生産性や創造性を高めるだけでなく、従業員の幸福感や健康にも繋がると主張しています。
- 心理的安全性のつくりかた 「心理的柔軟性」が困難を乗り越えるチームに変える
-
本書では、組織やチームにおける心理的安全性の重要性について説明しています。心理的安全性がある環境では、メンバーが自分の意見やアイデアを自由に言い合うことができ、問題解決に向けた意見交換が促進されます。その結果、創造性や生産性が向上するとされています。
石井氏は、心理的安全性をつくるための方法として、以下のポイントを提案しています。まず、リーダーが率先して自らの脆さや失敗を認め、メンバーにも同じように失敗を認めることを促すことが重要だとしています。次に、メンバー間の信頼関係をつくり、コミュニケーションを円滑に行うことが必要であると述べています。さらに、フィードバック文化を導入することで、メンバーがお互いにフィードバックを行いやすい環境をつくることができます。
また、本書では心理的安全性が不足している状況や、心理的安全性を高めるための具体的な手法やアプローチについても解説されています。組織やチームのリーダー、マネージャー、人事担当者など、多くの方に役立つ内容となっています。
- 恐れのない組織――「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす
-
「恐れのない組織――「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす」は、心理的安全性が組織に与える重要性に焦点を当てた本です。著者は、チームメンバーが意見を自由に述べ、ミスを恐れずに挑戦することが、学習、イノベーション、そして組織全体の成長に繋がると主張しています。本書では、心理的安全性がどのように築かれ、維持されるかについて具体的な事例や実践的なアドバイスが提供されています。著者は、リーダーシップの重要性やコミュニケーションスキル、フィードバックの方法などに焦点を当て、組織内での信頼と協力を育むための方法を探求しています。
また、心理的安全性がチームメンバーの自己表現やアイデアの共有にどれほど寄与するかについても詳細に解説されています。著者は、組織が従来のヒエラルキーや制約を超えて柔軟で前向きな文化を築くためには、心理的安全性の確立が不可欠であると強調しています。
ファシリテーション
- “問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション
-
この本は、創造的対話にフォーカスし、グループでの意思決定や問題解決に役立つデザインとファシリテーションの技術を紹介しています。著者は、グループ内の様々な視点やアイデアを掘り下げ、様々な問題を解決するための創造的な方法について議論しています。 本書は4つのセクションに分かれており、第1セクションでは、ファシリテーターの役割とスキルについて説明しています。このセクションは、創造的な対話とアイデアの共有に不可欠な技術やツールを紹介しています。 第2セクションでは、意思決定のためのゲームやエクササイズを紹介しています。これらのステップは、グループ内の意見の一致を促進し、最終的なアイデアや決定の採択に繋がります。第3セクションでは、グループが創造的なソリューションを見つけるためのワークショップや挑戦的な状況のケーススタディを取り上げています。第4セクションでは、自己啓発のためのツールや技術を紹介し、ファシリテーター自身が学習したスキルを促進するための方法を提供しています。 この本は、グループディスカッションやプロセス設計に興味を持つ人々や、新しい問題解決に取り組む企業やビジネスマンにとって、有用なリソースとなります。読者は、創造的な価値を生み出すための方法を学ぶことができ、グループ内のコミュニケーションやコラボレーションを向上させるために、本書の戦略やプラクティスを活用することができます。
職場学習論
- 職場学習論 新装版: 仕事の学びを科学する
-
『職場学習論 新装版: 仕事の学びを科学する』は、職場での学びに着目し、その科学的な理解を深めるための書籍です。 本書では、職場学習の本質を理解するために、人間の学習に関する認知心理学や神経科学の研究成果を取り入れ、職場学習の理論的枠組みを提示しています。 さらに、実際の職場での学びについても、具体的な事例を取り上げながら、職場学習の方法や効果的な学習環境の構築方法について解説しています。 本書では、職場における学びの重要性や、学びの効果的な促進方法、学習者の視点などを分析し、すべての職場従事者にとって役立つ知識を提供しています。
- 主体的に動く アカウンタビリティ・マネジメント
-
「主体的に動く アカウンタビリティ・マネジメント」は、組織内での個人の責任と行動を強化し、アカウンタビリティ(説明責任)の文化を構築する手法に焦点を当てた本です。著者は、組織全体がより効果的で持続可能な成果を達成するために、各個人が主体的かつ責任を持って行動することの重要性を提唱しています。
本書では、アカウンタビリティの概念やその実践的な側面について詳しく解説されています。著者は、明確な目標設定、進捗のモニタリング、フィードバックの重要性を強調し、個人としての自己管理と組織内での協力が組み合わさったアプローチが成果を最大化すると説明しています。
具体的なケーススタディや実践的なツールを通じて、アカウンタビリティを向上させる方法が提示されています。著者は、リーダーシップやチームワークを通じて組織文化を変革し、個々のメンバーが自発的に目標に向かって行動するための手段を示唆しています。
この本は、組織内での効果的なアカウンタビリティの構築に関心を持つリーダーや組織メンバーにとって、具体的なステップと実践的なツールが提供される一冊です。
行動経済学
- 行動経済学が最強の学問である
-
「行動経済学が最強の学問である」は、行動経済学の力を強調し、経済学やビジネスにおいてその影響を示す本です。著者は従来の合理的な経済行動モデルに疑問を投げかけ、人間の心理や行動に焦点を当てる行動経済学の重要性を強調しています。本書では、人々が合理的ではない行動をする理由や、情報の処理や意思決定において生じる誤りについて解説しています。また、心理学や経済学を融合させ、実際のビジネスや政策への応用例を示しています。著者は、行動経済学がビジネス戦略や政策立案において有益であるだけでなく、個人の意思決定にも大きな影響を与えると説明しています。
この本は、読者に対して合理的な行動の限界を理解し、より現実的で実践的なアプローチを模索することの重要性を示唆しています。行動経済学の理論と応用についての洞察を提供し、経済や社会の様々な側面において行動経済学の価値を強調しています。
統計
- 心理学・社会科学研究のための調査系論文の読み方 改訂版
-
論文を読むには、研究者がどのような意図でその文書を書き、
その分析手法を使ったかを読み取る力が必要になる。
「統計を使った論文が読めるようになる」ことを目的とした本書は、
その手法が使われた理由と結果の意味が理解できるよう解説のポイントを厳選。
論文には決して書かれることのない部分を補いつつ、
書き手の視点から論文を読む筋道を解説する。
改訂版では効果量や95%信頼区間などについての記述を追加し、
近年の情勢により合わせた構成となっている。
- 質問紙調査と心理測定尺度―計画から実施・解析まで
-
本書は、質問紙調査を一度も経験したことのない初学者が、最初に学ぶべき基礎知識をひととおり身につけることができるテキストです。調査の実施計画・方法から、心理測定尺度の使い方・作り方、結果の整理・解析、論文・レポートの書き方、研究者としての心構えまで、気鋭の著者陣が独自の尺度開発や調査法の授業をうけもった経験を活かして詳しく解説しています。また、近年欠かせなくなっているウェブ調査やテキストマイニングの基礎知識についても盛り込みました。
多変量解析
- 教育・心理系研究のためのデータ分析入門 第2版―理論と実践から学ぶSPSS活用法―
-
「本当にこの分析方法で正しいのか」
「分析の解釈はこれでいいのか」
「最終的にはどのように論文にまとめればよいのか」
という学生の声をよく耳にする。
本書はそれらの疑問にこたえて、専門分野に必要な統計の基本概念や理論、
SPSSの基礎的な操作方法、APAに準拠した論文への記載例をまとめた。
また、妥当性の論証に関する検証方法や有意性検定の問題点に対処する方法、
効果量の目安となり得る最新の知見なども紹介している。
基礎から実践、まとめまで、教科書としても使える役立つ一冊。
- SPSSで学ぶ医療系多変量データ解析 第2版
-
複雑な現象をデータで捉える多変量解析は高度な数学理論のうえに成り立っているため、
初心者にとっては優れた統計ソフトウェアの助けが不可欠だ。
本書では各解析手法の解説を“解析のしくみ”と“解析の実際”の2章構成とし、
SPSSの操作手順とあわせて理論と実用の両面から学ぶことができる、
初心者にもある程度の経験を積んだ人にも役に立つ。
広く支持されてきた初版をSPSSのバージョンアップに伴い改訂。
構造方程式モデリング
- はじめての共分散構造分析 第2版―Amosによるパス解析
-
「はじめての共分散構造分析 第2版―Amosによるパス解析」は、共分散構造分析に初めて取り組む人や、Amosを使用する人向けの入門書です。 本書は、共分散構造分析の基本的な概念から始まり、パス図の作成方法、検定方法、モデルの改善方法、複数グループ比較、メディエーション・モデレーション分析、マルチレベル分析など、さまざまなトピックを網羅しています。 Amosを使用して解析するための具体的な手順や、解析結果を読み解くためのポイントも詳しく説明されています。また、初心者でも理解しやすいように、図や例題を多数掲載しています。 本書を読むことで、共分散構造分析の基礎知識を習得し、Amosを使って自分自身のデータに適用することができるようになるでしょう。
- SEM因果分析入門―JUSE‐StatWorksオフィシャルテキスト
テキストマイニング
- テキストマイニング入門 ExcelとKH Coderでわかるデータ分析
-
「テキストマイニング入門 ExcelとKH Coderでわかるデータ分析」は、テキストマイニングについて初心者向けに解説した書籍である。テキストマイニングとは、大量のテキストデータから情報を取り出す技術であり、ビジネスや研究などの分野で活用されている。
本書では、テキストマイニングの基礎知識から、ExcelやKH Coderといったツールを使った実践的な分析手法までを掲載している。Excelを使用した場合、テキストデータを分かりやすい形式に変換し、グラフやピボットテーブルを使って分析することができる。また、KH Coderを利用することで、より深い分析や高度な処理が可能になる。
本書では、テキストデータから得られる情報を活用するための応用例も紹介されている。例えば、商品レビューの分析を通じて、製品の改善点や顧客ニーズを把握することができる。また、SNSの分析によって、オンライン上での企業の評判や顧客の反応を捉えることができる。
「テキストマイニング入門 ExcelとKH Coderでわかるデータ分析」は、テキストマイニングに興味があるビジネスマンや研究者にとって、実践的な一冊となっている。
- 社会調査のための計量テキスト分析―内容分析の継承と発展を目指して【第2版】 KH Coder オフィシャルブック
-
さまざまなテキストの内容分析を質・量ともに実現する計量テキスト分析を徹底的に解説。よりよい分析のために研究事例のレビューを増補し、KH Coder3にも対応した待望の第2版。
社会調査などの研究で盛んに用いられている実績あるテキスト型データ分析用フリーソフト、「KH Coder」の利用方法と実際の解析事例を紹介する。
第2版では最新版 KH Coder3 に対応したレファレンスマニュアルを掲載するとともに、成功した研究事例のレビューと共通点から計量テキスト分析のよりよい利用方策を考えるための「第8章 研究事例に学ぶ利用の方策」を収録。
スライドデザイン
- パワーポイント スライドデザインのセオリー
-
「パワーポイント スライドデザインのセオリー」という書籍は、パワーポイントのスライドデザインについての基本的な考え方やポイントを解説した書籍です。 本書では、スライドの作成にあたっては、フォントや色などの基本的なデザインをベースにして、視聴者に伝えたい情報を明確に伝えることが重要であることが強調されています。また、スライドのレイアウトやデザインを適切に調整し、ビジュアルの見栄えを良くすることも大切であると述べられています。 さらに、本書ではスライドの伝え方についても解説されています。例えば、スライドの枚数を適切に調整することや、スライド内のテキストや画像などの配置を工夫することで、視聴者にわかりやすく伝えることができるようになります。 最後に、本書ではスライドの伝え方についての考え方やポイントだけでなく、実践的なデザインテクニックも紹介されています。これらのテクニックを使うことで、視聴者にとってより魅力的で効果的なスライドを作成することができます。
- 医療者のスライドデザイン: プレゼンテーションを進化させる、デザインの教科書
-
『医療者のスライドデザイン: プレゼンテーションを進化させる、デザインの教科書』は、医療関係者がプレゼンテーションのスライドデザインについて学ぶための実践的なガイドです。
本書では、プレゼンテーションの目的や対象者を明確にすることから始め、視覚的にわかりやすく伝えるデザインの基礎から応用まで詳しく解説されています。具体的には、配色やフォント、レイアウト、画像の選び方や使い方など、デザインに関する基本的な知識から、アニメーションやチャートの作り方、プレゼンテーションのストーリーテリングについても詳しく説明されています。
また、医療関係者にとって特に重要な、医療情報の正確性や法的規制、倫理的な問題にも触れられています。このような情報をプレゼンテーションに反映させる際にも、デザインの力を借りて、視覚的に分かりやすく、かつ正確な情報を伝えることができます。
本書は、実践的なデザインの知識を身につけたい医療関係者や、プレゼンテーションのスキルアップを目指す人におすすめの一冊です。
- プレゼンテーション Zen 第3版
-
「プレゼンテーション Zen 第3版」は、プレゼンテーションの質を向上させるためのアプローチを提供する本です。著者はプレゼンテーションを芸術として捉え、観客との共感や説得力を高めるためにはデザイン、ストーリーテリング、デリバリーの要素が絶妙に組み合わさるべきだと説いています。
本書では、プレゼンテーションのデザインにおいて視覚的な要素の重要性やレイアウトの工夫、カラーパレットの活用などに焦点を当てています。また、ストーリーテリングにおいてはエンゲージメントを高める方法やメッセージの構築についてのアドバイスが充実しています。
さらに、デリバリーにおいては声の使い方や身振り、スピーチのリズムなど、プレゼンター自身の表現力向上に関する具体的な技術が紹介されています。著者はこれらの要素が統合されることで、オーディエンスに対して深い印象を残すプレゼンテーションが可能となると説明しています。
本書は、プレゼンテーションのスキル向上を目指す人々にとって実践的で具体的なアドバイスを提供する一冊です。